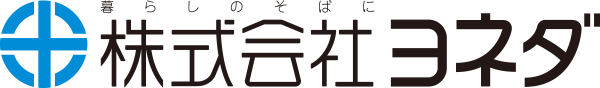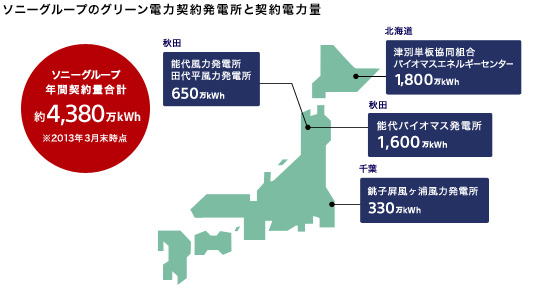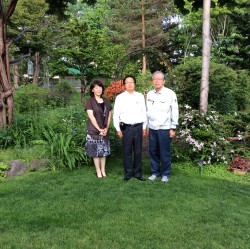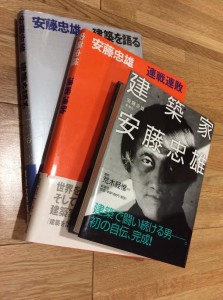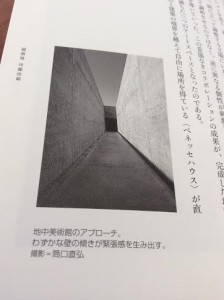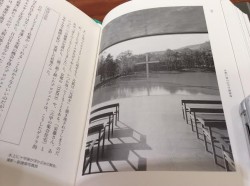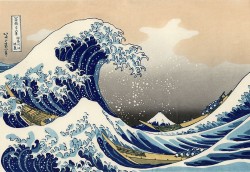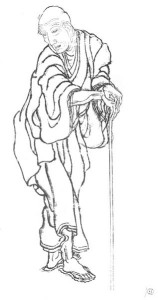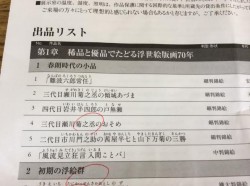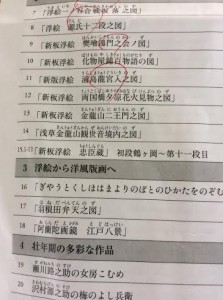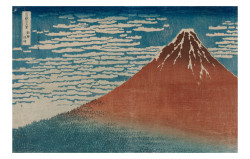翌日はレンタカーで娘の住む網走に向かいました。
直線道路を走ると時々太陽光発電のパネルが見える。
緯度のせいかずいぶん角度が急に見える。
娘のとってくれた網走湖畔の観光ホテルに落ち着く。
オーナーさんを知っているらしく、学生時代ヨット部の彼女はたまにオーナーさんのヨットに乗せて頂いているらしい。
午後から休みの彼女が来てくれ、山の中腹の蕎麦やさんに向かう。
その間も彼女に都度都度電話やメールが入ってくる。
急に車を止めて、ハザードランプをつけて長々と話している・・。
蕎麦やさんに偉丈夫の男性と奥さんとおぼしき女性が入ってくる。
娘は知っている様子で挨拶を交わす。
「父です。」と紹介をされる。
「京都から来られましたか?」
と声をかけられる。
市長さんらしい。
その日は娘のアパートを見に行ったり、コーヒーを飲んで分かれる。
網走市立郷土博物館や野取岬を観光。
網走市立郷土博物館はフランク・ロイド・ライトの影響の強い田上義也氏の設計。
ヒグマやキタキツネ、鷲、ハヤブサなどの剥製が迎えてくれる。
彼らのテリトリーと意識させられる。
夜は一人で市内の鮨屋へ。
一人でマスターと四方山話をしながら杯を干す。
「網走は住むのに良いところですよ。災害もないし・・。」
翌日は朝から車で知床に向かう。
湿原の横や海岸べりの直線道路をどんどん走る。
1時間半ぐらいで知床の起点、宇登呂(ウトロ)に着く。
知床自然センターや知床五湖を観光する。
羅臼岳も遠望する。
ウトロに戻り、ウトロ漁協婦人部なる食堂で時鮭定食。漁師さんも入っておられ少し混んでいる。
添えられた塩辛も美味しい。
昼下がり、海から硫黄岳までの観光船に乗る。
海鳥のコロニー、ミンク鯨、イルカに遭遇。
豊かな自然を感じる。
冬は寒いやろなぁ~。
ホテルに帰り仕事の終わった娘と焼き肉屋で夕食。
仕事の話、家の話諸々・・・。
甥っ子(長男の息子)が可愛くて仕方ないらしい。
携帯の待ち受けにしている。

カウンターで食べていたが、ふとみると足元に大きなバックを置いている。
「大きいバックやなぁ~?」
「パソコンとカメラが入っている。パソコンが重いねん。・・・いつでも出動せなあかんでな・・・。」
帰りに(バックを指して)
「もってみ。」
ずっしりと重い・・。
翌朝ホテルをチエックアウト。
支払いは既に娘が済ませていた。
お礼のメッセージを入れると
「あのあとまたクマが出て大変でした。お気をつけて。」
との事でした。
だんだん子供が成長していっていると感じ嬉しいような、ちょっと寂しいような複雑な気持ちの親父でした。