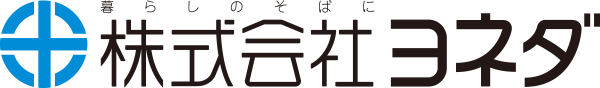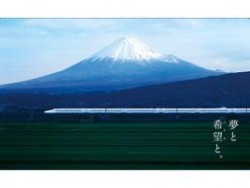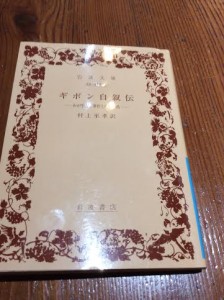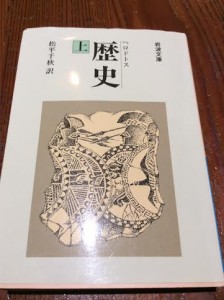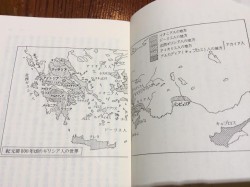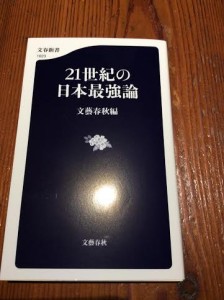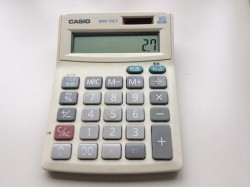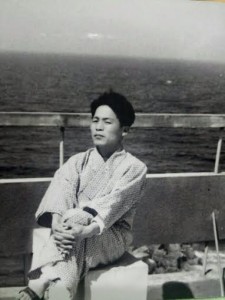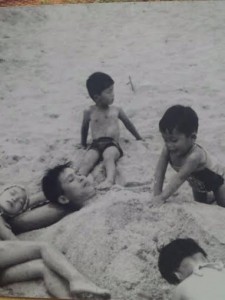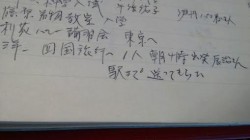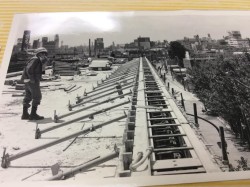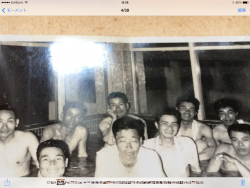某日都内に出張があり、早朝「のぞみ」で帰社。
東京駅のコンコースを歩くとゴミ一つ落ちてなく、掃いて清めたようになっている。
「う~ん、このオペレーションは凄い!」
何時もどおり、品川名物貝づくし弁当を客席にてほうばる。
考えてみると、誰とも一言も話さず、パソコンでExpress予約やホテルも予約し、時間通りにかなりの頻度で精確に新幹線が動き、あれだけの乗降客がいる東京駅が朝にははいて清められたようになっている・・・・、「日本国の達成した凄さ!」ではないかとつくづく思います。
車中にて「ギボン自叙伝 わが生涯の著作との思い出」を読みました。
エドワード・ギボン(1737-1794)は英国の歴史家で古代ローマ帝国の興亡を記した古典大作「ローマ帝国興亡史」の著者として有名です。
著者はロンドン近郊の比較的裕福な家庭に生まれ、14歳でオックスフォード大学へ父親から入れられる。勉学は余りせず当時はやりの宗教論争に凝りだしたため、父親が心配しスイスのローザンヌのプロテスタントの牧師に預けられる。そこで語学や古典の勉学を始めた。
「・・さて私は仏蘭西語・ラテン語の翻訳に際し、大変良い方法を採ったが、自分の成功に鑑みて学生諸子も倣われるようお勧めしたい。私は先ず、キケロー、ヴェルトーのような、文体の純粋と優雅とで最も定評のある作家を選んだ。それから、たとえばキケローの或る書簡を仏蘭西語に訳し、原文を棄てて単語や熟語が記憶からすっかり消えてしまうと、今度は自分の仏蘭西文を再び自分の書き得る限りのラテン語に訳し返し、その上で私の不完全な訳文を、このローマの雄弁家の流麗・優美・端正な文章と一句一句比較した。
・・・私は、全部の書簡、全部の演説、及び修辞学や哲学の最も重要な諸論文を、一意専心且つ愉快に読破した。
・・・私は言葉の美を味ひ、自由の精神を呼吸し、彼の教訓や模範から、人間の公民として又個人としての心構えを理解した。
・・・雄弁と知慮との書庫と言ふべきこの偉大な作品を読み終へると、次にはラテンの古典を一、歴史家、二、詩人、三、雄弁家、四、哲学者、の四群に分ちブラウトゥス、サルスティウスの時代から、ローマの国語と帝国との衰微に至るまで、年代順に閲読しようといふ更に遠大な計画を立てた。そしてこの計画をローザンヌ滞在の二十七箇月(1756年1月ー1758年4月)に、殆ど遂行した。」
以前に読んだ「古代への情熱 シュリーマン自伝」シュリーマン著を思い出します。
幼い頃に読んだトロイ戦争の物語に感銘を受け、トロイ戦争は実際にあったと本気で信じたシュリーマン。その夢を実現すべく、少年時代から働きずくめに働いて蓄財し、そして語学を十数ヶ国語独学で学び文献を漁り、遂にトロイの遺跡の発掘に成功するお話です。幼年時に一緒に発掘を夢見た女性とは数日間の求婚の遅れで夢かなわず、後に結婚し一緒に夢を果たします。
その語学の取得の仕方が圧巻で、文法書によって文字と発音を覚え、文章を丸暗記し部屋を歩き廻りながら暗誦を繰り返すことによって超ハイスピードで語学を取得して行きました。
丁度、ギボンの語学の取得に似ているように思いました。
「ローマ人の物語」塩野七生著(全43巻)読んだことがあり、「ローマ帝国興亡史」もいずれ手にとって見たいという思いもあり著者のギボンの名前に反応し本屋で購入しました。「ローマ人の物語」を全部読むには3年位かかりました。その間に同じ著者の「海の都の物語 ヴェネネチィア共和国の一千年」(全6巻)や「わがともマキャベリ-フィレンツェ存亡」なども関連で横道にそれ?読みました。
最近はアマゾンで本を思い出したように買っており、購入して最後まで読まない本も多いです。新聞やネットで興味を持ちワンクリックで注文みたいなパターンですが積読(つんどく)が多いように思います(苦笑)
この本のお蔭で「ヘロドトス 歴史」松井千秋訳などの歴史書を関連で読み始めました。紀元前5世紀頃のギリシャの諸都市とペルシア帝国との抗争の歴史です。豊富な説話や風俗習慣が書かれており読みやすいです。
・・・
後日譚。
後日本屋に行きました。
思いつくまま8冊程度購入しました。
購入した「21世紀の日本最強論」文芸春秋編に福島清彦氏が「衝撃の国連レポート『世界一豊かな日本』GDPを超える新経済統計 日本の強みは設備・インフラ力」と言う文章がありました。
成熟した先進国がGDPで経済の豊かさを計ることからの脱却お話です。既にEUでは2020年の長期戦略についてGDPと言う言葉を使っていません。若者の学力向上や貧困者数削減などの五項目の具体的な数値目標を定めています。
新しい「物差し」は2009年に米国のコロンビア大学のステイグリッツ教授(2001年ノーベリ経済学賞受賞)が主査となってまとめました。仏のサルコジ大統領から教授に「GDPに代わる新しい経済指標のあり方を考えて欲しい」と諮問され考えられました。「暮らしの質を計る」(金融財政事情研究会)として邦訳されているそうです。
その「物差しの要素」は
①国民の頭脳能力である人的資本
②ヒトが生産した資本
③国民の信頼関係である社会資本
④農業・鉱物資源を中心とした天然資本
だそうです。
私が初夏の早朝、東京駅で「心地よい」感じたのは①と③かもしれませんね。
機会があられましたらご一読あれ。