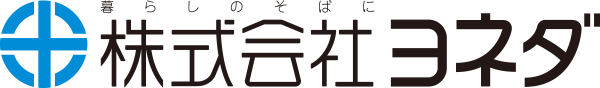2022年4月10日
 ー
ー
4月に入り一気に気温が上がってきました。
少し動くと汗ばむほどです。桜も散り始めました。
今年は雨が降らなかったので随分と楽しめました。

4月に入り経営方針発表会を行いました。
前日に入社した9名の新入社員も出席しました。

例年は3月下旬の入社ですが今年は入社研修のY.T.A(ヨネダトレーニンングアカデミー)や他の行事の会場が重なる為に4/1となりました。
早速にY.T.Aの開校式を行い二回の外部研修も含めた6月末迄の長丁場の入社研修を行います。
新入社員の方は体調管理をして頂き徐々に社会人生活に慣れていって頂きたいと思います。

間話休題。先日「ドラッガー わが軌跡 知の巨人の秘められた交流」P.F.ドラッガー著 上田惇生訳を読みました。
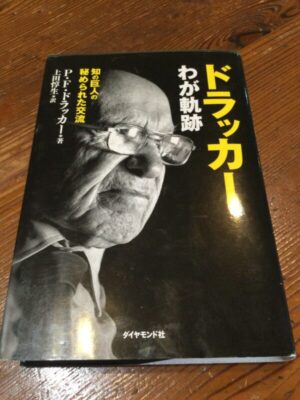
何かの拍子に日経新聞電子版の「私の履歴書」のアーカイブでドラッカーさんの分を読み返した為です。最近の連載だったように記憶していましたが、2012年でもう10年前の事でした。その連想ゲームでこの本を取り寄せました。読み始めると興味深く一気に読了しました。
会社でも以前にベストセラーになった「もし高校野球部の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」岩崎夏海著(通称「もしドラ」)を皆で読書感想文として読んだことがありました。
先の経営会議の部門のリーダーの方の講演の中でも「ドラッカー目線で見直した○○部の仕事」・・・「真の顧客は誰か?」をテーマに意欲的な内容でした。
P.F.ドラッカーは1909年にハプスブルク家が最後に統治した国家、オーストリア=ハンガリー帝国の首都ウィーンで生まれました。父は外国貿易省高官(政府三高官の一人、工業生産を指揮)、母はオーストラリア人女性として初めて医学教育を受けた女性です。文化レベルの高かったドラッカー家では知識人が集まるサロン的役目も果たしていて、精神学者のジークムント・フロイトや後の20世紀を代表する経済学者になるヨーゼフ・シュンペーター、作家のトーマス・マン等錚々たる人々が集まっていました。
・・・このくだりを書いていて思い出したことがあります。以前オーストリアのザルツブルク駅(モーツアルトの生家がある)でハンガリーの首都ブタペスト行きの列車を見たことがありました。「あ〜この列車に乗って行ってみたいな・・」と感じたことです。冬にミュンヘンの工業見本市に行った時の思い出です・・・
8歳の時に両親と組合食堂でフロイトと出会ったドラッガーは両親にフロイトと握手させられました。別れた後に両親から「この日のことだけは覚えておきなさい。オーストリアで一番偉い人、もしかしたらヨーロッパで一番偉い人にお会いしたんだよ。」「皇帝より偉い人?」「そうだよ。」と言われ強く記憶に残ったそうです。
1918年にオーストリア=ハンガリー帝国(人口6000万人)が第一世界大戦に敗れハプスブルク家は崩壊し、オーストリアは人口600万人のアルプスの小国になります。大戦によって廃墟と化したことで何百万年もかけて築き上げてきた文明がガタガタに崩壊します。ヨーロッパ全体で1000万人以上の人が殺され、文明を立て直す人まで全て失いました。4歳のドラッガーは父と叔父とトマーシュ・マサリク(のちのチェコスロバキア大統領)の「これはハプスブルク家の終わりというより、文明の終わりだね。」の会話が最も古い記憶となります。後々まで「文明とは何か?」を考え続けるドラッカーの原体験となります。
ウィーンの幼少時代、市内の私立学校に通います。そこで小学校4年9歳の時に最高の教師に出逢います。ミス・エルザ先生とミス・ゾフィー先生です。エルザ先生は生徒の得意を伸ばすのを得意としており子供たちは先生を崇拝していました。子供に潜在能力がありながらそれを活かしていないと執念を燃やすタイプでした。エルザ先生の妹であるゾフィー先生は子供中心で生徒は先生に群がっておりいつも子供を膝の上に乗せていました。男子生徒にも裁縫を習わせるなど革新的な考えの持ち主でした。教え方は生徒の間を歩き回って、あちこちに座り込み、言葉を使わず教えこみました。生徒の動きを見、その子の小さな手に自分の手を重ね絵筆を正しく持つように誘導しました。
・・・ミス・エルザは私の字を直せず、ミス・ゾフィーは私を工芸家にはできなかったが、私は抜き去りがたい影響を受けた。学ぶ楽しさと教える喜びに救いがたいほど魅せられてしまったのだ・・・(「私の履歴書」より)
著者は著名な文筆家でありながら、ヨーロッパ時代の大学の非常勤講師を初めに米国ではニューイングランド地方の小さな女子大学ベニトン大学やクレアモント大学で95歳まで教壇に立ち続けました。
著者がギムナジウム(寄宿舎学校)の13歳の時にオーストリアが第一次世界大戦に敗れ、ハプスブルク家の最後の皇帝が退位し、共和制が宣言されました。戦争には負けた日だが社会主義者の街になったウィーンでは勝利の日でありました。青年社会主義同盟のオルグ、女子医学生から「自発的デモ行進」の先頭を行進しないかと誘いに著者は応じました。多くの工員や徒弟のグループも合流し労働歌を歌いながら著者は赤旗を掲げて行進しました。前方に水溜りが見えました。いつもは水溜りをわざわざ歩く著者であったが、その日は自分が選んだ水溜りでなく行進に強制された水溜りでした。著者は進路を変えようとしたが、後ろからのざっくざっくという大群の足音、物理的な圧力に押されて水溜りを通り抜けさせられました。すぐに著者は後ろにいた女子医大生に赤旗を渡し隊列を離れました。家に帰って訝った母から「具合でも悪いの?」と尋ねられ「最高だよ。僕のいる場所ではないってわかったんだ。」と答えました。11月の寒い日に著者は自分は「観察者」だということを確信します。こうして「時代の観察者」P.F.ドラッガーが誕生しました。
17歳でギムナジウム(寄宿舎学校)を卒業後ドイツに移住、ハンブルクで事務見習いとして働く。就職と同時にハンブルク大学法学部に籍をおく。図書館に入り浸りの乱読の日々。当時のヨーロッパでは大学に行かなくても、就職すれば責任ある大人として扱われました。特にハンブルク、アムステルダム、ロンドン、バーゼルなどの商都では、家業を継ぐべき最も優秀な男子は大学にいかないものと相場は決まっていました。著者の父は進学を希望していました。家系的には高級官僚、法律家、医師の家系でありました。著者の見立てでは学者の道に進むのは自分は才能が通用するか判らず、実業の世界であれば二流でもやっていけると考えたようです。又、アルプスの小国になったオーストリア。大戦前の帝都を懐かしむウィーンに留まることを著者はよしとしなかったようです。
ハンブルク時代には文筆家として記念すべき出来事があります。ドイツの経済季刊誌に大学入試の準備のために書いた論文「パナマ運河の貿易に果たす役割」が掲載されました。その結果ヨーロッパ有数の経済週刊誌オーストリア・エコノミストの編集会議に帰郷時招待されました。副編集長であるハンガリー人のカール・ポランニー※と親しく付き合うようになる。
※ ハンガリーの解放運動に関わる。『大転換』を執筆。後にアメリカのコロンビア大学で客員教授となり、一般経済史を教えた。市場社会。社会統合のパターン。交易、貨幣、市場の経済史的定義を論じる。
・・・ポランニー一家の五人兄妹は極めて優れた兄妹であり、全員が名をなし、当時のヨーロッパ社会に大きな足跡を残しました。兄妹全員が自由でありながらブルジョア的でもリベラルでもない社会、繁栄しつつも経済に支配されない社会、共同体でありながら共産的でもない社会の実現という、同一の大義に奉じました。全員が別の道を歩きました。それはちょうど聖杯を求めて旅立った円卓の騎士たちを思い起こさせました・・・
・・・しかし彼らが重要な意味を持つのは、彼ら自身や彼らの生涯のゆえではない。それは彼らの大義やその挫折のゆえだった。彼らのそれぞれが、大きな事を成し遂げた。だがそれらのものは、それぞれが目指したものではなかった。彼ら全員が、「社会による社会の救済」を信じていた。しかし、やがて諦めさせられ、落胆させられていた。彼らは才能に恵まれていたが、歴史上の大物にはならなかった。いずれも重要人物というよりは興味深い人物であるにとどまった。だが彼らの挫折にははるかに重要な意味があった。それは、ホップズとロック以来300年とまでは言わなくとも、フランス革命以来200年にわたって、西洋が追い求めてきたものそれ自体が、意味のないものであった可能性を示すものだったからである・・・(本書より)
著者は1年3ヶ月後にフランクフルトに移り米国系証券会社で証券アナリストになリました。その仕事は1929年のニューヨーク証券取引所の崩壊によって失われました。直ぐにフランクフルト最大の発行部数を誇る夕刊紙に就職し金融記者になリました。かなり早く昇進し2年後には国際面を担当する記者兼編集者兼論説委員になりました。他方ハンブルク大学の法学部に在籍し国際法で博士号を1932年に取得。国際法のゼミでは休みがちな老教授の代講を行う。その他雑誌にも寄稿。ヒットラーが政権をとったらドイツを離れるであろうことを意識していたました。ナチスが著者と関わりをもたないようにするためユダヤ人の政治哲学者フリードリッヒ・ユリウス・シュタールの政治思想について論じました。直ぐに発禁処分になリました。やがてヒットラーが政権をとったためにドイツを離れイギリスを経て1937年に米国に旅立ちました。
ヒットラーの全体主義にも嫌気が差してイギリスのマーチャントバンクで証券アナリスト兼パートナー補佐として働き始めるが、経済学者ケインズの授業を聴講したのをきっかけに自分のやっている事に疑問を持ち始めます。「ケインズもまわりの学生もみんな考えているのは金と物の動きだ。自分もマーチャントバンクでいかに金を増やすか考えている。自分にとて関心のあるものは人間や社会であったのではなかったか・・・。」米国へあてもなく移住するきっかけとなりました。
・・・米国に渡った著者は大学の非常勤講師とライターをやりながら自分が今までにヨーロッパで見たことをまとめる作業に取り掛かりました。・・・ヨーロッパの歴史を考えてみると・・・1776年にジェームス・ワットが蒸気機関を発明し大量生産が行われるようになりました。いわゆる産業革命です。1776年はアダム・スミスによる「個人がそれぞれに自己の利益を追求自由に経済活動に励もさえすれば、結果として社会全体の利益が達成される」という「ブルジョア資本主義」の理論が誕生した年とも重なります。資本主義の「物的基盤」と「理論基盤」の両方が揃い記念すべきスタートを切った歳です。しかしながら実際には社会全体が豊かになるのではなく、生産手段を持っている資本家だけが豊かになっていきました。それに不満を感じた人々は「生産手段を資本家から取り戻せば格差が解消され、全ての人々が幸せになれるはずだ」と新しい理想を掲げる人々が出てきました。その典型がマルクス主義です。ロシアは第一次大戦中、社会主義革命によって労働者が生産手段を労働者が奪い取ったものの実際には一部の特権官僚階級だけが潤い、大衆は貧しいままになりました。資本主義と社会主義に失望した人々は自然と「脱経済至上主義」へ救いを求めます。当時用意されていたものは国家社会主義という「ファッシズム全体主義」しかありませんでした。イギリスやフランスは民主主義に対する脅威として国家社会主義に進むことを躊躇し、ついにはなんとしても阻止しようとしました。それが米国・ソ連を巻き込み第二次世界大戦になりました。
著者は第一次世界大戦の世界の状況を見て、国家社会主義の本質は「脱経済至上主義」であったと考えました。著者は米国で1939年に第一作『経済人の終わりー全体主義はなぜ生まれたか』を出版しました。「経済人」とはエコノミックアニマルの事です。経済のために戦争する人々、あるいは休戦する人々、経済至上主義の世を生きる人々の事です。巻末に「経済至上主義に基づいた資本主義も社会主義も問題を解決できない。行き着く先は国家社会主義という事になる。それでも人間を幸せにはしてくれない。何か別の答えがあるはずだ。何か別の答えを見つけなければならない。」で『経済人の終わり』は終わっています。この本は後の英国首相のウィンストン・チャーチルに大絶賛されます。彼は『タイムズ』に書評を書いてくれただけでなく、首相就任後陸軍幹部候補生学校の卒業生全員にこの本を配ってくれました。
その『経済人の終わり』の答えが二作目『産業人の未来ー改革の原理としての保守主義』1942年になります。著者はこの本の中で、今後は産業人が未来を作っていく事になるーと述べています。現在の社会においてほとんどの人が、なんらかの形で組織に属しながら働いていると言えます。著者はその流れを見て、社会の構成要素の組織というものに目を向けるようになりました。単純に言ってしまえば、全ての財とサービスが組織で生み出され、全ての人が組織で働いているとするならば、それらの組織をより良いものにしていけば、組織の集まりである社会も良くなるはずだーというのが彼の考え方です。
私たちは人生の大半を、会社とはじめとする組の中で過ごしながら、物的・精神的に双方の豊かさをそこから受けています。社会の構成要素である組織の一つ一つがどう運営されるかによって、人間は幸せにも不幸にもなりえる。それならば資本主義や社会主義といった「イズム」にかわるものとして、組織の運営の仕方(=マネジメント)にこそ注目すべきではないか、と著者は考えました・・・(参考文献より)
著者は大企業を内から調べる必要を感じていました。しかしながら、大企業で働いた経験もなく、そもそもいかなる大組織で働いた事も無かった。それ以外は『産業人の未来』を書いた後の二年間は極めて順調に過ごしていました。1942年にはこじんまりとした女子大のベニトン大学で常勤の教員となり、ハーバードとプリンストンからも招きを受けていました。1943年にはもの書きとしても一本立ちしていました。『ハーパーズ』、当時絶頂期にあった『サタデーイブニングポスト』にも書いていました。政府機関の仕事も入っていました。政府機関の仕事を通じて著者はフルタイムの仕事よりもパートタイムのコンサルテイングが自分に向いている事を自覚しました。さまざまな会社に組織の研究を申し込むもことごとく断られたり、危険分子と見た人もありました。(ウェステイングハウス社)
・・・突如GM広報担当者から著者に電話があり「副社長ドナルドソン・ブラウンの代理としてお電話しました。もしや当社のマネジメントと組織について調査されるお気持ちはありませんか?」
ドナルドソン・ブラウンに出会うと「『産業人の未来』を拝読しました。私たちは企業のガバナンス、組織構造、社会での位置付けなど、あの本でお書きになっているような事を現場で取り組んできました・・・しかし、GMでもとくに私たち年代の者は、はっきりとではありませんが、何か先端的な事に取り組んでいるという意識はずっと持っていました。1920年にGMを立て直したピエール・デユポンは随分前に引退しました。」
「その後を継いで二十年間CEOを務めてきたアルフレッド・スローンも、引退すべき年はとうに過ぎています。戦争が終われば引退するでしょう。私たちもはるかに若いですが、一緒に引退するつもりです。」
「しかし、GMのマネジメントや構造は出来上がって四分の一世期経っています。見直す必要があります。あなたが自動車産業にも企業経営にも詳しくない事は存じております。でもあなたの本を読んで、私はあなたが、政治学者あるいは社会学者としてGMを調べ、そのマネジメント、構造、内外の関係を明らかにしてくれるのではないかと思ったのです。」「まず全体像をつかんでいただくために、幹部十人ほどにお会いしてはどうでしょう。調査の方向づけができたところで、私がCEOのスローンにご紹介します。この調査ではスローンが一番大事です。彼はミスターGMです。私たちは皆スローンの補佐みたいなものです。」
著者はGMの幹部から話を聞けば聞くほど、彼ら一人ひとりがいかに有能で個性豊かであろうとも、結局は脇役に過ぎない事を実感させられていたのだった。主役はあくまでもアルフレッド・スローンだった。ブラウン、コイル、ドレイスタット、その他GM幹部の全員が、自信満々の堂々たる人物だった。しかしスローンの名を言うときは声の調子が変わった。「スローンさんも賛成です。」と言うときはあたかも聖書を引用しているかの感があった・・・(本書より)
・・・少し話を聞けば、彼がなぜ巨大組織の中で権威を保ち続けているのかすぐに理解できた。社交辞令を使うような人間ではないのだ。
「あなたが仕事をしやすいようにしてあげることが私の義務です。経営委員会にもどんどん顔を出すのがいいでしょう。何を調べ、どんな結論を下すか。すべてあなたの自由です。注文は一つだけ。『こんな助言なら気に入ってもらえそう』などと決して妥協しないでもらいたい。」
会議が終わると、いつも私をオフィスへ招き、質問や意見はないかと聞いてきたものだ。「でもスローンさん。私に反対意見があったところで聞き入れてもらえるものでもないでしょう」「私が裸の王様になっているか見極める必要があるのです。GMの中ではだれも教えてくれませんからね」
経営者として注目すべきスローンの資質は私情をはさまないことだった。この点では異常なまでに徹底していた・・・
著者はこの調査によって『企業とは何か』を書くことになります。出版されてすぐに評判になり、大企業の組織改革のテキストとして広く受け入れられることになります。
写真は『GMとともに』アフフレッド・スローン著。(ドラッカーの『企業とは何か』は大系としてのマネジメントを確立する為の本であり、アルフレッド・スローンの著書は経営のプロとしてのマネジメントが書かれています。スローンはGMの大株主でしたが、彼の競争相手のヘンリー・フォードのようにオーナーのままではなくプロのマネジメントによって経営される会社にGMを育て上げました。スローンの意図はドラッガーと違うアプローチでGMを論じたわけです。本も経営書として大変な名著となり永く読み継がれています。)
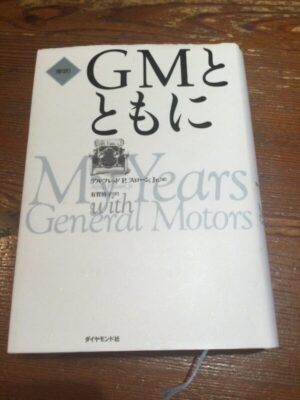
人の幸せの為に「組織」を「マネジメント」する。『もしドラ』や『マネジメント エッセンシャル版ー基本と原則』などを読んだときはほとんど時代の背景が理解できていなかったように思います。もっと言いますと著者の動機や意図も判っていなかったように思います。又、1900年代の二度の大戦の間、欧州の人々が考えた事や当時の米国の様子が興味深く書かれています。ドラッカーを巡りオーストリア、ドイツ、英国、米国でのさまざまなビジネスで関わった人々や知識人との交流が描かれており、どの章から何度読み返しても味わい深いです。訳者の後書きに「それぞれの世界に、通だけが知っていると言う超一流のものがある。なぜかはわからないが、通の間でしか知られていない。あたかも通たちが、門外不出、秘伝たるべきことを誓い合っているかのようである。まさに本書がそのような本だった。」その言葉がわかるような気がしました。
参考文献:マネジメント ドラッカー 上田惇生著 100分de名著ブックス